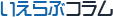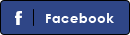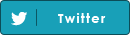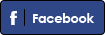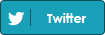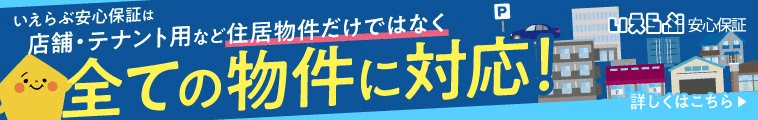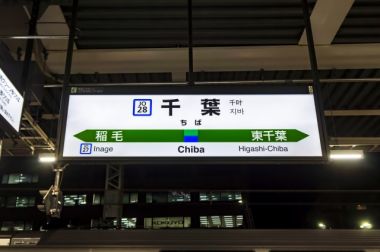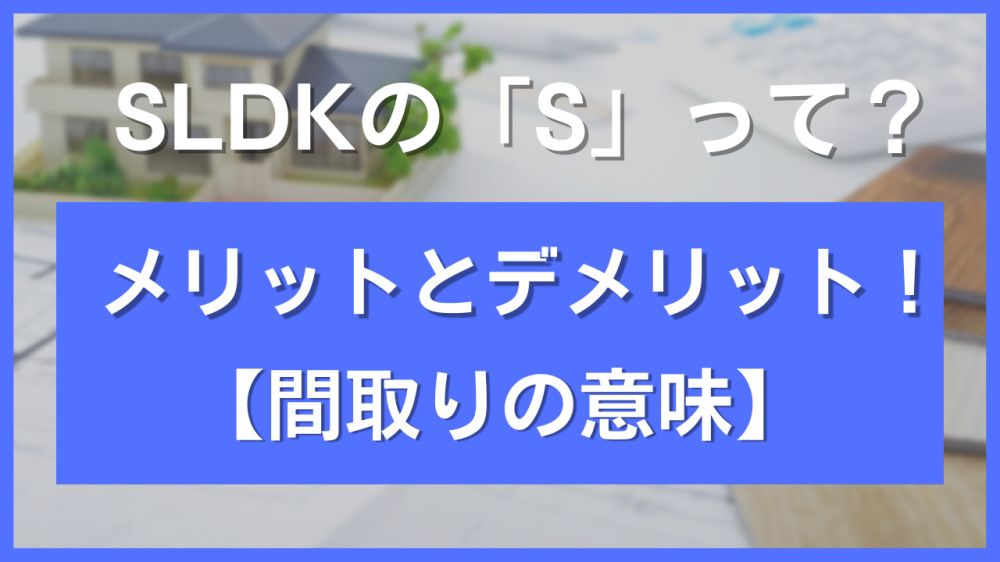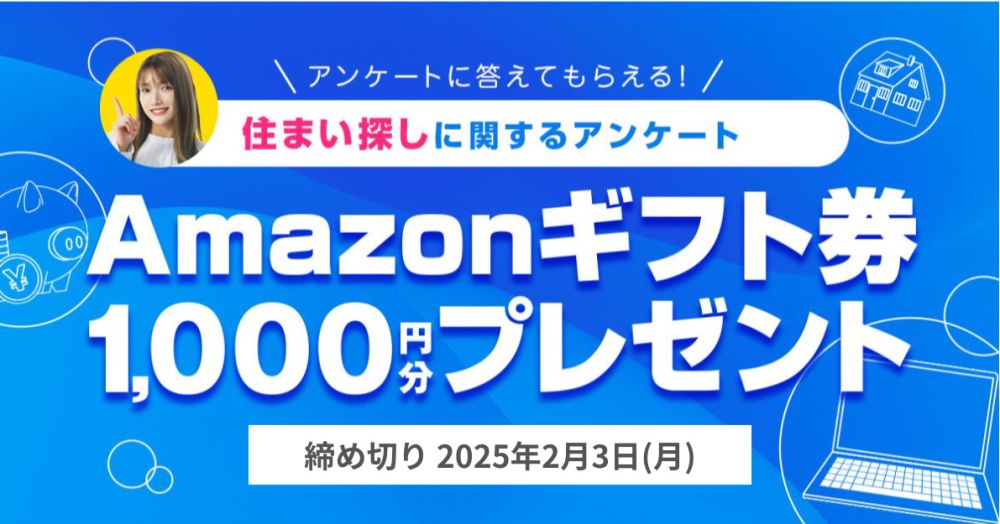- いえらぶ不動産コラム>
- 住まいのノウハウ>
- 弁護士へ相談すべき不動産トラブルとは?

目次
不動産は高額な価格で取引されていたり、生活の起点となる重要なインフラであることから、一度、トラブルが発生してしまうと問題が大きくなってしまうことが少なくありません。
そうなってしまうと、当時者同士での解決は難しいため、双方の利益のためにも専門家へ相談することが解決の近道となります。
今回は不動産に纏わるトラブルのうち、法律の専門家である弁護士に相談すべき事案や相談の手続きや必要になる費用についてまとめました。
不動産トラブルを抱えている、もしくは不動産トラブルに巻き込まれそうな方にとって役煮立つ内容となっているのでぜひ、最後までお付き合いください。
弁護士に相談すべき不動産トラブルの内容

一言で不動産トラブルと言っても、売買取引きや賃貸取引、賃貸の経営などその内容は多岐にわたります。
そして、そこで発生するトラブルの種類も豊富です。
まずはトラブルの起きやすい不動産売買と賃貸経営をクローズアップして、弁護士に相談すべき事案を見ていきましょう。
不動産売買で発生しやすいトラブル
不動産売買では事前の調査不足や説明不足などが発端となりトラブルが発生してしまいます。
たとえば、共有持分や借地権、抵当権や質権などの権利関係に関わるトラブルです。
購入しようとしている不動産の所有権は複数人による共有持分だった場合、すべての所有権を移転しなければ、まともな権利行使をおこなうことはできません。
しかし、多くの場合、意見が割れたり、高齢のため、満足な意思表示ができないなど、すべての少勇者の同意を取り付けることは指南の技です。
また、法令上の制限を受ける場合のトラブルも深刻です。
市街化調整区域内の土地をマンション用地として購入したとしても建築許可が出ることはありませんし、宅地造成法の制限がある場合は自治体の求める基準に適合させるために想定以上の出費が必要となることもあります。
また、契約不適合責任の範囲内かどうかという点もトラブルになりやすい点です。
賃貸経営で発生しやすいトラブル
賃貸経営において発生するトラブルは主に貸主と借主との間で起こります。
もっとも多いのは入居者に対して立ち退きをしてもらいたい場合です。
宅建業法は入居者保護の趣旨が強いため、一度、入居してしまうと簡単に入居者を追い出すことができません。
たとえば、他の入居者に対して過度は宗教活動や特定の政党のための政治活動をおこなったり、深夜に暴れまわって散々、迷惑をかける入居者がいて、警察に通報したとしても民事不介入を理由に解決することはできません。
しかし、いくら迷惑行為を続ける入居者であっても、賃料の不払いや暴行事件を起こす、実は反社会的勢力やそれに準ずる団体の構成員だったなど(信頼関係の欠如)に該当する事由が無い限り、強制的に出ていってもらうことはできません。
また、退去時の原状回復費用の負担についても、よく揉めます。
国土交通証の示すガイドラインや紛争防止条例では通常損耗は貸主負担、故意や過失など借主の責めに帰す事由による損耗等があればその復旧費用を借主が負担するとされています。
しかし、実際には室内での喫煙や無断でペットを飼育していた場合、または善管注意義務違反などに基づいて費用の請求をおこなったとしても納得して支払いに応じる入居者はごくわずかです。
不動産トラブルを弁護士へ相談するメリットとデメリット

とはいえ、不動産トラブルと抱える当事者の多くは、弁護士への相談を躊躇しています。
当然のことながら、弁護士へ依頼することで費用がかかりますが、実はそれを上回るメリットがあるという点にも目を向ける必要があります。
不動産トラブルを弁護士へ相談するメリット・デメリット
不動産トラブルを弁護士へ相談するメリットは早期解決が期待できる点や弁護方針を示してくれる点です。
実は不動産のトラブルでは、法的根拠がないにもかかわらず感情的になってこじれていることが少なくありません。
そこに第三者かつ法律の専門家である弁護士の介入を受けることで当事者同士が冷静になり裁判にならずとも和解への緒を見つけやすくなります。
しかし、一方で弁護士へ依頼することのデメリットもあります。
それは、弁護士費用が発生してしまうことや相手方との関係が破綻してしまう可能性がある点です。
弁護士への相談や依頼には相応の費用が必要です。
抱えているトラブルによって受けている損害の大きさと弁護士費用とを事前に比較することで弁護士への依頼が適当かどうかの判断をすることが可能です。
また、一度、弁護士の介入を受けると、そのインパクトは大きく、相手に対して徹底抗戦の構えを示すと同時に人間関係が破綻してしまいます。
とくに争族と呼ばれる、不動産の絡む相続においては親兄弟や親戚などとの間で関係性が破綻してしまうことから、弁護士への依頼には熟慮の上、決定することをおすすめします。
弁護士に依頼する場合の手続きと必要な費用
熟慮を重ねた結果、弁護士への依頼を決意したら、まずは相談してみると良いでしょう。
相談ではトラブルの内容を説明して弁護方針を聞くことができます。
また、依頼した場合にはどのくらいの費用が掛かるのかの見積もりをもらうこともできます。
ちなみに、弁護士費用は着手金や報奨金、日当や手数料、必要経費などいくつかの項目に分けられた支払いが必要となります。
弁護士に依頼するときに必要な費用の内訳

ここからは実際に弁護士に相談するときから必要となる費用の具体的な金額を見ていきます。
相談料
弁護士へ依頼するかどうかを相談するときに支払うものが相談料です。
1時間5千~1万円ほどに設定している場合が多く、初回無料としている法律事務所もあります。
相談時に本当に法的な手続きが必要なトラブルなのかどうかや、そもそも弁護士への依頼が有効なのかどうかなど案件ごとに具体的な内容を打ち合わせます。
なお、この相談は弁護士事務所に赴きおこなう他、電話相談や出張相談をおこなっている弁護士もいるので事前に調べてみると良いでしょう。
着手金
弁護士への相談の結果、依頼するとなった場合、委任契約書を交わします。
そして前払いで着手金を支払うこととなります。
案件により金額は異なりますが、不動産に関するトラブルの場合10~30万円ほどになることが多いようです。
着手金はトラブルが解決したかどうかに関わらず、必要となる返却されることのない費用となるため、依頼を決めるときには診療に決断しましょう。
報奨金
報奨金はトラブルが解決された場合に支払いが必要となる費用です。
トラブル解決の要件が金銭の要求だった場合は、その金額のうち、何割かを支払う取り決めをおこなうことが多いようです。
ちなみに報奨金は成功報酬のため、トラブルが解決しなかった場合、支払いは不要です。
その他費用
弁護士に依頼するにあらり、裁判所への出廷があるなど、弁護士を拘束する時間が発生する場合は日当の支払いが必要です。
また、手続きに必要な文書の作成費用や調査のための交通費や印紙代なども実費請求されることとなるので注意が必要です。
まとめ
不動産トラブルが発生する背景には説明不足や確認不足や調査不足など、単純な原因であることが少なくありません。
しかし対象が高額で取引されていたり、人の生活と密接な関わりを持つ不動産だからこそ、こじれて大きなトラブルへと発展しがちです。
しかし、同じようなトラブルは前例があったり、法的根拠を示すことで容易に解決することができることもあります。
不動産トラブルに特化したサイトなどもありますので、まずは気軽に相談してみることがから始めてみてはいかがでしょうか?
いえらぶでは物件や不動産会社の口コミを見て比較できます。
よりクリアな情報から、あなたにぴったりの
いい家を選んでみませんか?
お部屋を探す
Writer この記事を書いた人
- いえらぶコラム編集部
- いえらぶコラム編集部は、皆さまの住まい探しに役立つ知識や、暮らしを豊かにする情報を発信していきます。